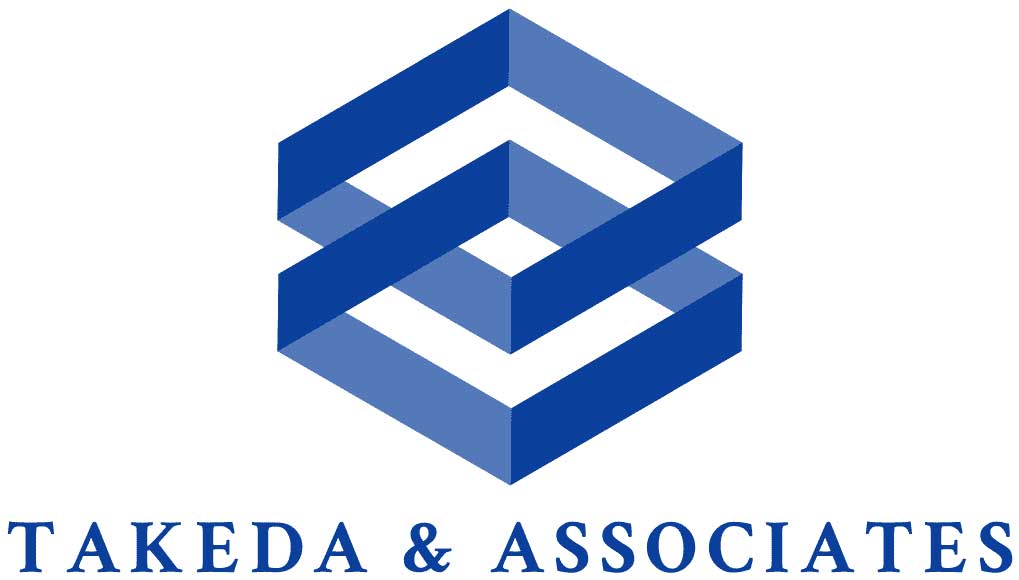こんにちは。税理士の竹田です。
今回は、外資系企業や海外取引の多い法人が税務調査で指摘を受けやすい項目についてご紹介したいと思います。
それは、ロイヤリティ(使用料)の源泉徴収もれです。
ロイヤリティってなんだ?と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、こちらについては後程ご説明いたします。
ロイヤリティの源泉徴収漏れに関しては、過去は米アップルの子会社で日本法人の「iTunes」が、知的財産の使用料をめぐって音楽・映像の配信サービスに関して所得税の源泉徴収もれを指摘され、約120億円の追徴課税をされたこともニュースになっていました。
税務調査官も指摘した時のインパクトが大きいため、調査の際に重点的に調べているケースもあります。
Index
1.そもそもロイヤリティ(使用料)とは?
日本の所得税法上では、源泉所得税の対象となるロイヤリティ(使用料)の定義は、所得税法第161条第1号第十一号に規定されています。
所得税法第161条第1項十一号
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
上記を読んでいただくとお分かりになるかと思いますが、権利関係の使用料など明らかに該当するについてはイメージしやすいのですが、特別の技術による生産方式~などかなりあいまいなものもあり、実際の事例に落とし込むと判断に迷うものも多々あります。
2.源泉税率は?
使用料に関する源泉税率は所得税法第213条に規定されており、20%の税率が適用されることになります。
また、原則として所得税に対し2.1%の復興特別所得税が課せられるため、合計で20.42%の税率となりますが、租税条約の規定により、復興特別所得税が免除される場合があります。
3.租税条約の適用について
租税条約が適用される国については、所得税法第162条に異なる定めがある場合の規定があり、日本と他の国との間で租税条約が結ばれている場合で、ロイヤリティに関し別の規定が定められている場合には、租税条約の規定が適用されることになっています。
従って、判断にあたってはまず国内法を確認するとともに、租税条約の規定がある国との取引である場合には、租税条約の確認が必要ということになります。
4.OECDモデル条約の定義は?
OECDモデル条約では、ロイヤリティは以下のように定義されています。
文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は 産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領されるすべての種類の支払金をいう。
日本の所得税法における使用料と租税条約で規定されている使用料は、必ずしも一致するものではないですが、概ね一致しているものと考えられます。
5.留意が必要な具体的取引は?
様々なケースが想定されるのですが、具体的には、開発に関する技術やデータの提供が知的財産権の使用料に該当するといったケースや、海外親会社が権利関係を保有しており、その権利を使用して日本でソフトウェア等の販売をしている場合に、親会社に支払う売上の一部が権利の使用料と判断される場合など、取引の実態を詳細に理解して判断する必要があります。
特に親子関係の取引であれば、契約書などの書面で取引内容や条件が定められていないケースもあり、税務調査で結論に至るまでにかなり時間を要する場合もあります。
また、場合によっては、弁護士もしくは弁理士に対し、法律的な観点からのアドバイスを求めることも必要と考えられます。
6.おわりに
海外取引を行っている法人に関しては上記に該当しうる取引が潜在的にあり、源泉漏れのリスクを認識していたとしても判断に迷われるケースもあると思います。
弊社では法人顧問契約だけでなく、個別でのご相談も賜っておりますので相談したいという方は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。
竹田
こちらのクリックもよろしくお願いします。↓